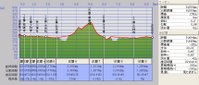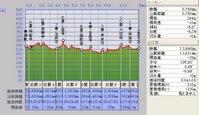|
| Google Earthで作成 |
また、峠道といえばその領界を区切る場合、境界石なども目にするのだが、それもない。秩父往還の歴史に、江戸の頃秩父からは善光寺に、甲斐国からは秩父観音霊場札所へと、信仰・行楽を兼ねた人の往来が結構あった、というのだが、それならもう少々道標・丁石といった道標があってもいいような気がするのだが、これも「四国遍路道」の視点からの物事の見方に陥っているのかもしれない。
それはともあれ、ゆっくりと山小屋で体を休め2日目、雁坂峠から三富村広瀬へと下ることにする。
本日のルート;
初日
西武秩父駅から西武バス・川又バス停へ>川又バス停>入川橋>登山口>石の道標>水の本>雁道場>突出峠>樺小屋・避難小屋>だるま坂>地蔵岩展望台>昇竜の滝>雁坂小屋
2日目
雁坂峠に向かう>雁坂峠>下山開始>沢>峠沢右岸>峠沢を左岸に>林道に出る>雁坂トンネル口>鶏冠山大橋>道の駅 みとみ>甲府市駅
雁坂小屋からの日の出;午前5時
 なにせ前日は午後8時に寝ているわけで、午前4時過ぎには寝覚め。小屋の電灯が灯るともに起床。
なにせ前日は午後8時に寝ているわけで、午前4時過ぎには寝覚め。小屋の電灯が灯るともに起床。5時少し過ぎた頃日の出を見る。山稜の名はよくわからないので、カシミールの3D描画機能カシバードで作図しチェック。唐松尾山から雲取山そして和名倉山に続く稜線の、雲取山の左手から太陽が顔を出しているように思える。
小屋の北には昨日歩いた突出尾根、そのずっと先には両神山らしき、特徴的な山容が見える。そのまた、すっと先に見えるのは雲なのか谷川連山なのか。
●黒岩尾根ルート
小屋の前に左方向に向かって「天幕場 黒岩道」の案内がある。黒岩道とは国道140号・豆焼橋から1,050m等高線と1,100m等高線の間を進み黒岩尾根に入り、そこから尾根を巻いて1,828mの八丁の頭まで進み、八丁の頭の先から尾根筋を雁坂小屋へと向かう。
地図で見ると、雁坂小屋は黒岩尾根に乗っかっているようにも見える。雁坂小屋から黒岩道を少し進んだ先に小屋のお手洗いがあり、その建屋が道を覆っている。黒岩道が二級国道140号ルート、といった記事もあり、国道を跨ぐトイレとして紹介されている。
はっきりしたことはわからないが、突出峠ルート登山口にあった環境庁・埼玉県作成の秩父往還の案内には、突出峠ルートが一般国道と記されていたので、黒岩ルートは国道ではないかもしれない。とすれば、国道を跨ぐ云々は面白いが、お話に過ぎない、ということになってしまうようだ。
雁坂峠に向かう;7時20分
雁坂峠;7時35分(標高2,082m)
 比高差100m強を15分位上ると前面が開けた雁坂峠に到着。峠の南面は一面の草原となっており、昨日歩いた北斜面の針葉樹林と対照的な景観となっている。
当日は天気もよく富士山が顔を出す。カシミールの3D機能カシバードで峠から見える山稜をチェックすると、左手に水晶山(標高2,158m)。富士山は水晶山から古礼山(標高2,112m)、雁峠(標高1,780m程の鞍部)笠取山(1,953)に続く稜線脇から姿を見せているように思える。
比高差100m強を15分位上ると前面が開けた雁坂峠に到着。峠の南面は一面の草原となっており、昨日歩いた北斜面の針葉樹林と対照的な景観となっている。
当日は天気もよく富士山が顔を出す。カシミールの3D機能カシバードで峠から見える山稜をチェックすると、左手に水晶山(標高2,158m)。富士山は水晶山から古礼山(標高2,112m)、雁峠(標高1,780m程の鞍部)笠取山(1,953)に続く稜線脇から姿を見せているように思える。右手前方、今から下る谷合の先に見える尾根筋は雁坂峠から西に甲武信ヶ岳(標高2,475m)を経てグルリと逆時計周りに国師ヶ岳(標高2,591m)、奥千丈岳(標高2m409m)と続き、前面には笛吹川の谷間に落ちる乾徳山(標高2,016m)の尾根筋が見える。
 少々難儀したが、南アルプスの三伏峠や北アルプスの針ノ木峠と共に日本3大峠に数えられている雁坂峠をクリアした。いつだったか読んだ『今昔 甲斐路を行く 斎藤芳弘(叢文社』)の「雁坂口」の項に文学博士・金田一春彦氏が作詞した「雁坂峠」の歌が載っていた。金田一教授の先祖は武田氏の一族で、勝頼の代、武田一族が滅びたとき、甲斐から雁坂峠を越えて陸奥国、現在の盛岡に落ち延びたとのこと。
少々難儀したが、南アルプスの三伏峠や北アルプスの針ノ木峠と共に日本3大峠に数えられている雁坂峠をクリアした。いつだったか読んだ『今昔 甲斐路を行く 斎藤芳弘(叢文社』)の「雁坂口」の項に文学博士・金田一春彦氏が作詞した「雁坂峠」の歌が載っていた。金田一教授の先祖は武田氏の一族で、勝頼の代、武田一族が滅びたとき、甲斐から雁坂峠を越えて陸奥国、現在の盛岡に落ち延びたとのこと。峠を下った本日の最終点、三富村の道の駅にある石碑に刻まれたその歌は、 「三富広瀬は石楠花どころ 小径登れば雁坂峠 甲斐の平野は眼下に開け 富士は大きく真ん中に 大和武尊も岩根を伝い 日には十日の雁坂峠 東国目ざす武田の勢も 繭を葛籠の商人も 旅人泣かせの八里の道も 今は昔の雁坂隧道 川浦の湯から秩父の里へ 夢の通い路小半時」とある。
三富広瀬は今から道を下りバス停のあるところ。富士の眺めは前述の通り。大和武尊のくだりは「日本書記」によれば、「景行天皇の御代(2世紀頃)、陸奥国(東北地方)・常陸国(茨城県)を平定した日本武尊が、酒折宮(甲府市酒折に比定)に泊り、この峠を越へて武蔵国(埼玉県)から上野国(群馬県)に達し、碓井峠を越えて信濃国(長野県)・越後国(新潟県)の平定に向かったと伝説を指す(『古事記』のルートは異なる)。
歌にある「日には十日の」とは日本武尊が酒折宮で詠んだ「新治 筑波を過ぎて幾夜か寝つる」に対し、供のものが詠い返した「日日並べて夜には九夜 日には十日を」の歌をひく(『今昔 甲斐路を行く』より)」。
信玄率いる大軍が雁坂峠の難路を越したとの記録はないようだが、信玄の時代には峠から10か所ほどの狼煙台を繋ぎ、関八州の軍事情勢を伝えた、という。また前述の股の沢や真の沢に拓いた金山へとこの峠を越えていった、とも。さらに峠は甲斐府中から北東の鬼門にあり、罪人を甲斐の国から追放した道でもある。
軍勢ばかりでなく民衆も峠を越えた。山間村落での養蚕が盛んであった秩父、特に大滝や栃本の人々は大正時代までは繭を背負って峠を越え、甲州の川浦や塩山の繭取引所に。繭を運んだ。秩父の大宮より甲州のほうが近かったということである。
江戸時代、庶民の生活に余裕ができると信仰・行楽を兼ねた人々が峠を越えた。秩父からは甲斐の善光寺、身延山久遠寺、伊勢参り、甲州からは三峰、秩父観音霊場への巡礼のため峠を越えた。江戸時代には月に1万人以上の人が秩父観音霊場を訪れたという。
『甲斐国志』に、「嶺頭の土中ニテ古銭ヲ掘リ得ル事アリ。昔時往来ノ人山霊ニ手向ケセシ所ト云」とあるように、中世以降は峠の神にお金を奉納したのだろう。峠の語源は「たむけ;手向け」にあるとも言う。神に手を合わせたのだろう。ともあれ、日本武尊の伝説を引き、日本最古の峠道との記述もある歴史のある峠ではある。
●峠付近の植生
山梨県側
雁坂峠の稜線一帯には山地草原が見られる。この草原は山火事などによる森林破壊後の風のあたる斜面に成立した草原で、シモツケソウ、オオバギボウシ、ミヤコザサ、オオバトラノオ、イタドリ、アキノキリンソウ、シモツケ、ミヤマヨメナ、カラマツソウ、シシウド、マルバダケブキ、グンナイフウロ、キソチドリ、などが生育している。雁峠にも同様の草原が見られる。
シモツケソウ;ばら科。茎は約60㎝で葉は多くの枝葉からできている。
オオバギボウシ;ゆり科。花の茎は60㎝?100㎝で、葉より高い、若葉は食用。
ミヤコザサ;いね科。棹高30㎝?1mで北海道から九州の太平洋岸に野生
埼玉県側
一方雁坂峠の埼玉県側の斜面には、高木層にコメツガとトウヒの優占する亜高山針葉樹林が見られる。亜高山層はシラビソ、オオシラビソ、トウヒ、低山層にはコヨウラクツツジ、サビハナナカマド、ミネカエデ、シラビソ、草木層はマイズルソウ、ミヤマカタバミ、カニコウモリ、オオバグサ、バイカオウレンなどによって構成されている。
コメツガ;まつ科。常緑針葉高木。高さ?m?20mで本州の中・北部に分布。
トウヒ:まつ科。唐檜。常緑針葉高木で高さ20m?25m。
マイズルソウ;ゆり科。茎は???㎝で本州中部~北海道に分布」との記述があった。
下山開始;7時45分
沢;7時57分(標高1,970m)
峠沢右岸;8時42分(標高1,720m)
雁坂嶺には当然のことながら幾つもの切り込んだ沢筋がみえる。先ほど下山途中で見たささやかな沢筋もそのひとつであろうが、それら沢筋の水を集め、この地点では堂々とした沢となって下っている。
峠沢を左岸に;9時16分(標高1,500m)
峠沢右岸を40分ほどかけ標高200m強下げると3本ほどの木を渡した木橋がある。途中、行き会った方から木橋は凍って滑るため気を付けて、とのアドバイスがあった。ちょっと木橋に乗ったのだが、滑って危なそう。水勢の弱い箇所を見付け沢を渡ることにした。木橋で転んだら大怪我だった、かも。感謝。
林道に出る;9時50分(標高1,400m)
橋の少し上で峠沢は、雁坂嶺から甲武信ヶ岳への稜線上にある破風山(2.317m)の山腹から下ってきた「ナメラ沢」と合わさり名を「久渡沢」と変える。
雁坂トンネル口:10時33分(標高1,200m)
料金所の先、雁坂トンネルに入る道路を見乍らちょっと想う。川又から10時間以上かけて抜けた甲武国境の山塊を、トンネルを抜ければ10分程度で走り終える。それはそれでいいのだが、この便利さであり、逆に往昔の峠歩きの不便さは往々にして、現在の視点からの見方のように感じる。
少しニュアンスは異なるが、今昔の視点の置き方により、物の見え方が変わると感じたのは大菩薩峠超えの時。中里介山の『大菩薩』で机龍之介が何故に、わざわざ不便な山奥の大菩薩峠に立ち、不埒な所業を行ったのか疑問に思っていたのだが、大菩薩峠を歩いたとき、その道が江戸時代に開かれる以前の古い甲州街道であり、江戸の頃も甲州裏街道として人の往来があった、とのこと。 いまでいう「準幹線国道」であった、ということ。国道であれば、そこに主人公がいてもおかしくはないだろう。
●雁坂トンネル建設の経緯
◆昭和29年(1953)二級国道甲府・熊谷線として指定
往昔の秩父往還は、昭和28年(1953)には二級国道甲府・熊谷線として指定されている。熊谷・甲府を結んだ理由は、国道指定には10万人以上の都市を結ぶ必要があったからである。
秩父往還と中山道の分岐点には道標(熊谷市石原)「ちゝふ(秩父)道、志まふ(四萬部[しまぶ]寺)へ十一(里)」と刻まれた道標、秩父長瀞の「宝登山道」の碑も建っていた、という(現在は移されている)。四萬部寺は秩父礼所1番である。
◆当初の想定は雁峠ルート
既述の如く二級国道に指定された、といっても建設が進んだわけではない。昭和29年(1954)には建設促進期成同盟が結成され、昭和32年(1957)には両県の代表が雁峠で合流し、建設促進の協力を期している。
当初のルートは、滝川と豆焼沢が合わさる豆焼沢出合から八丁坂を刳り貫き、滝川本谷左岸から釣橋小屋上を通り水晶谷~古礼沢中流部を通り雁峠~燕山~古礼山直下をトンネルで抜けるルートだったようである。隧道計画も1000m程度であったとのこと。雁坂峠直下を抜くルートに変更となったのは昭和59年(1984)。国立公園の保護、地質調査の結果を踏まえての変更、と言う。
◆昭和30年代から50年代は進展なし
昭和32年(1957)には両県代表が雁峠で気勢を上げたにしても、建設省の動きは鈍く昭和30年(1955)代から50年(1965)代にかけて秩父は大滝村、山梨は三富村が中心となって活動するも状況の変化はない。
昭和34年(1959)には伊勢湾台風により山梨側・三富村の一之橋、二之橋、三之橋が破壊され、秩父側も二瀬ダムの道路が寸断される。この復旧工事により道路建設が少し進む。
昭和36年(1961)には二瀬ダムが完成、昭和45年(1970)には山梨側の広瀬ダムが完成。ダム工事の道が結果として国道建設促進の一助となっている。 昭和47年(1972)には、山梨側拐取工事率は50.4キロ。全体の42.4%。 一方埼玉側101.4キロ、全体の78.6%まで進んだ。最後の難関は雁峠である。 雁峠ルートに関し、昭和40年代後半;大きな壁が立ちはだかる。それは当時起こった環境問題への高い意識からの自然保護の問題。山梨側は亀田林業所の私有地であり用地取得は比較的楽であったようだが、秩父側は東大の演習林。環境保護の観点から反対に遭い、埼玉側の用地買収が難航した。
昭和50年(1975)には過去22年間に山梨47.8キロ、埼玉76.6キロの拡張舗装が行なわれ、未舗装部分は山梨の広瀬以北6.5キロ、埼玉の雁峠登山口近くの14.8のキロとなったが、未だ雁峠トンネルの見通しが全く立たなかった。
◆昭和56年(1981)雁坂峠ルートが決定
昭和56年(1981)になり雁峠から雁坂峠ルートとの結論を建設省が出す。昭和58年(1983)には三富村の城山トンネル(三富村下釜口)が開通。昭和59年(1984)には建設省が来年度予算に雁坂トンネル工事費を計上。この年をもって雁坂ルート工事正式決定としているようだ。
雁坂峠は石楠花の群生地でもあり、トンネルを抜く計画を描き、昭和60年(1985)に計画概要発表。全長6.5キロ、幅7mのトンネルでありふたつの県を跨ぐため国の直轄事業となった。
昭和60年(1985)には雁坂トンネルの直ぐ南の広瀬トンネルの起工式。雁坂トンネルの前段階といったものである。昭和63年(1988)には広瀬トンネルが久渡沢を渡る鶏冠山大橋が完成、更にその先、笛吹川に架かる西沢大橋も着工となった。
◆平成元年(1989)着工。平成10年(1998)開通
平成元年(1989)に川浦で着工式。平成2年(1990)大滝側も工事開始(詳細は記述「大滝道路」に)。平成6年(1994)、トンネル避難坑が開通。平成10年(1998)開通した。
開通に際し、自然保護の観点から秩父側のバイパス道・大滝道路が間に合わず、旧国道を半年間使うことになったため、大渋滞を引き起こしたことは前述の通りである。
●山梨側の雁坂トンネルへのアプローチ道路建設
雁坂トンネルへのアプローチ道路建設は、秩父側は従来の国道140号とは別にバイパス国道140号・大滝道路の建設をもって雁坂トンネルと繋いだ。同様に山梨側もいくつかバイパス工事をおこないトンネルと繋げている。
大滝道路と同じく「雁坂トンネルと秩父往還(山梨県道路公社)」の資料をもとにまとめておく。
◆広瀬バイパス
「広瀬バイパスは」は、東山梨郡三富村広瀬地内の未改良区間、交通不能期間の解消及び「雁坂トンネル」へのアプローチ道路として昭和57年度(1982)より道路改築事業に着手し、「雁坂トンネル」の開通に合わせて平成10年(1998)4月に完成した延長3,700mのバイパス。
このバイパスは急峻な山岳部と渓谷を通過するため六ヶ所のトンネルがある。「西沢大橋(橋長360m)」は、県内初の橋梁形式をもつループ橋であり、秩父多摩国立公園・西沢渓谷入口のシンボル的な橋となった。「鶏冠山大橋(橋長270m)」は、大きな渓谷を渡るため塗装の必要のない鋼材を山梨県において初めて採用した橋である、と記す。
古い地図がないため、旧国道140号がどのルートか不詳であるが、広瀬バイパスは雁坂トンネルから広瀬ダム湖の南まで強烈なルート取りをおこなっている。雁坂トンネルを抜けると石楠花橋で、久渡沢の崖を避け、すぐに広瀬トンネルに入る。トンネルを抜けると再び鶏冠山大橋で久渡沢を跨ぎ対岸の山稜を強烈なカーブのループ橋で西沢渓谷を跨ぎ、南に向かい久渡沢を渡り返し、広瀬ダムに沿って下る(同様の目的で東山梨郡牧丘町成沢と塩山市藤木間にも窪平バイパスが建設されているが、ちょっと場所が離れすぎているので省略する)。 秩父側も山梨側も雁坂トンネルへのアプローチ道路としては、旧国道を使うことなくバイパスで繋いでいた。
鶏冠山大橋;10時42分(標高1,150m)
当日は、なんとなく地味色の橋であり、同行のひとりから、この橋は使われなくなった橋かなア、などとの感想も聞かれたが、上述塗装の必要のない鋼材故の「地味さ」加減であったのだろうか。
それはともあれ、橋桁したから少し進むと道標があり、道の駅は林道を離れ土径へと右に折れる。久渡沢に向かって標高を30mほど落とし、久渡沢に架かる橋手前にでる。
道の駅 みとみ;10時59分(標高1,100m)
山梨市駅
広い道の駅にもかかわらず、バス停の案内が無い。彷徨っているとささやかな市バス停留所の案内があり待つこと十分ほど。無事市バスに乗り、途中温泉に寄る仲間ふたりと分かれ山梨市駅に到着。
慣れない自動特急券・指定券の販売機に苦戦し、ぎりぎりで特急甲斐路に間に合い、一路家路に向かう。







 順路が変わった要因は、秩父往還のメーンルートの変遷に負うところが大きいようだ。室町時代の秩父往還は名栗→山伏峠→芦ヶ久保→横瀬→大宮郷→皆野→児玉→鬼石が中心となっており、秩父観音巡礼はこの道か、吾野通りと称される、飯能→正丸峠→芦ヶ久保→横瀬→大宮郷がメーンルートであり、札所番付もその往還に沿ったものとなっている。
順路が変わった要因は、秩父往還のメーンルートの変遷に負うところが大きいようだ。室町時代の秩父往還は名栗→山伏峠→芦ヶ久保→横瀬→大宮郷→皆野→児玉→鬼石が中心となっており、秩父観音巡礼はこの道か、吾野通りと称される、飯能→正丸峠→芦ヶ久保→横瀬→大宮郷がメーンルートであり、札所番付もその往還に沿ったものとなっている。
 スラブ上でしばし眺めを楽しんだ後、大日如来へと向かう。右手が絶壁となった狭い山道を、怖さのあまり左手の崖に生える草木を握りしめ進む。これだけでも結構怖いのだが、その先には岩峰が屹立する。大日如来はその岩峰の上に安置されている。宝暦2(1752)年、西村和泉守作とのことである。
スラブ上でしばし眺めを楽しんだ後、大日如来へと向かう。右手が絶壁となった狭い山道を、怖さのあまり左手の崖に生える草木を握りしめ進む。これだけでも結構怖いのだが、その先には岩峰が屹立する。大日如来はその岩峰の上に安置されている。宝暦2(1752)年、西村和泉守作とのことである。 岩船観音で時刻をチェックするに、既に12時。もうこれは12時14分発の小鹿野町営バスには到底間に合わない。後は成り行きで段取りを組むことにして奥の院から下山し、仁王門前まで下りる。時刻は12時36分。
岩船観音で時刻をチェックするに、既に12時。もうこれは12時14分発の小鹿野町営バスには到底間に合わない。後は成り行きで段取りを組むことにして奥の院から下山し、仁王門前まで下りる。時刻は12時36分。 観音霊場巡礼をはじめたのは大和・長谷寺を開基した徳道上人と言われる。上人が病に伏せたとき、夢の中に閻魔大王が現れ、曰く「世の人々を救うため、三十三箇所の観音霊場をつくり、その霊場巡礼をすすめるべし」と。起請文と三十三の宝印を授かる。黄泉がえった上人は三十三の霊場を設ける。が、その時点では人々の信仰を得るまでには至らず、期を熟するのを待つことに。宝印(納経朱印)は摂津(宝塚)の中山寺の石櫃に納められることになった。ちなみに宝印とは、人というものはズルすること、なきにしもあらず、ということで、本当に三十三箇所を廻ったかどうかチェックするために用意されたもの。スタンプラリーの原型、か。
観音霊場巡礼をはじめたのは大和・長谷寺を開基した徳道上人と言われる。上人が病に伏せたとき、夢の中に閻魔大王が現れ、曰く「世の人々を救うため、三十三箇所の観音霊場をつくり、その霊場巡礼をすすめるべし」と。起請文と三十三の宝印を授かる。黄泉がえった上人は三十三の霊場を設ける。が、その時点では人々の信仰を得るまでには至らず、期を熟するのを待つことに。宝印(納経朱印)は摂津(宝塚)の中山寺の石櫃に納められることになった。ちなみに宝印とは、人というものはズルすること、なきにしもあらず、ということで、本当に三十三箇所を廻ったかどうかチェックするために用意されたもの。スタンプラリーの原型、か。 秩父が34観音になった時期については、諸説ある。16世紀後半には観音霊場巡礼が全国的になり、西国・坂東・秩父観音霊場をまとめて巡礼するようになってきた。で、平安時代に既に京都に広まっていた「百観音信仰」の影響もあり、全国まとめて「百観音」とするため、どこかが三十三から三十四とする必要がでてきた。霊場としては秩父霊場が歴史も浅かった、ということもあり、秩父がその役を受け持つことに。ために、大棚観音こと、現在の第2番札所真福寺を加え、三十四ヶ所と改められた、とか。もっとも、大棚観音が割り込んできたので、その打開策として「百観音」を敢えて提唱した、とか諸説あり真偽の程は不明。 ともあれ、諸説あるも、34の札所が成立したのは室町時代の天文年間(1532-1555)と言われる。
秩父が34観音になった時期については、諸説ある。16世紀後半には観音霊場巡礼が全国的になり、西国・坂東・秩父観音霊場をまとめて巡礼するようになってきた。で、平安時代に既に京都に広まっていた「百観音信仰」の影響もあり、全国まとめて「百観音」とするため、どこかが三十三から三十四とする必要がでてきた。霊場としては秩父霊場が歴史も浅かった、ということもあり、秩父がその役を受け持つことに。ために、大棚観音こと、現在の第2番札所真福寺を加え、三十四ヶ所と改められた、とか。もっとも、大棚観音が割り込んできたので、その打開策として「百観音」を敢えて提唱した、とか諸説あり真偽の程は不明。 ともあれ、諸説あるも、34の札所が成立したのは室町時代の天文年間(1532-1555)と言われる。